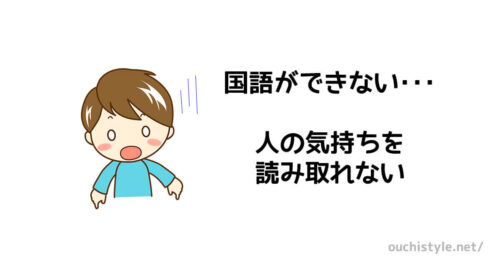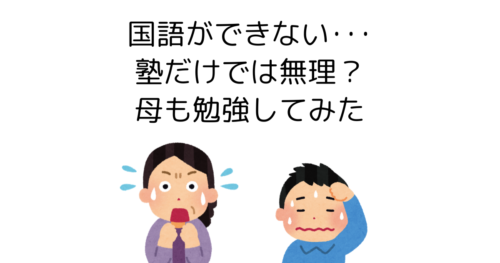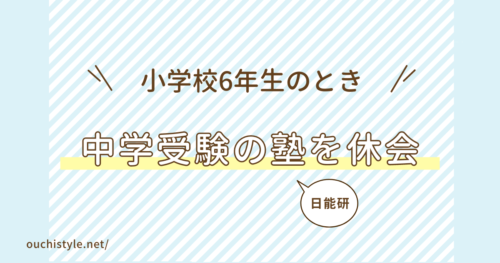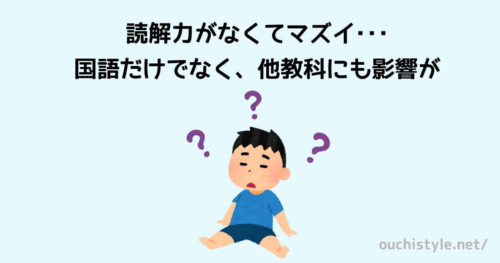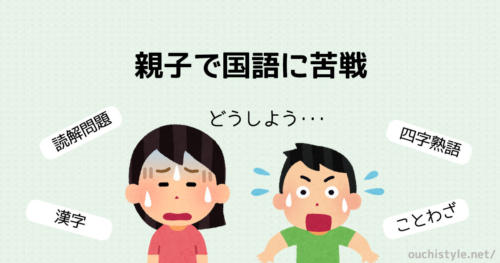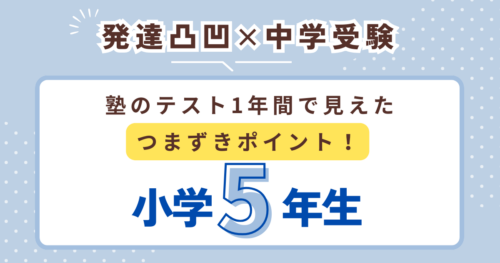中学受験5年生になると、勉強の内容も生活リズムも少しずつ変わっていきますよね。
特に発達凸凹のある子どもにとっては、「やることが増える」「ペースが速くなる」ことで、気持ちも体もついていかない時期だと感じます。
わが家も、日能研の学習力育成テスト(旧:カリキュラムテスト/通称カリテ)に追われながら、気持ちが上向いたり沈んだり…そんな1年でした。
成績が上下するたびに一喜一憂していましたが、今振り返ると、点数よりも「勉強への向き合い方」が少しずつ変わっていったことのほうが大きな成長でした。
この記事では、5年生の1年を「春・夏・秋」で振り返りながら、発達凸凹のある子がつまずきやすかったポイントや、成長につながった場面を書いていきます。
どんなテスト?5年生で変わること
学習力育成テストは、授業の理解度を確認するテストです。4年生までは「確認テスト」のような感覚でしたが、5年生からは一気にレベルが上がります。
・4教科しっかり出題
・応用問題が増える
・時間配分がシビア
まさに“模試の練習”のような内容ですね。
発達凸凹の息子は、文化祭で気に入った学校の志望校はあるものの、目の前のことしか見えず、やる気があるのか、ないのかという状態。
- 勉強に入るまで時間がかかる
- 気持ちの切り替えが苦手
- 問題の読み方が雑
- こだわりや得意科目がある
- 苦手なことには向き合わない
単元の問題を解き、テストに間に合わせるように、家庭での勉強スケジュールがキツかった~。
生活リズム・解き方・語彙力、テストでの時間配分など、「ここが課題なんだな」と色々と見えてきた1年になりました。
新5年生スタート
新学年が始まり、ケアレスミスを防ぐにはどうしようかという話になりました。
これは本人の性格や、身についたやり方もあり、個々のパターンがそれぞれですよね。
我が家の場合、息子の性格は
- 周りが見えない
- 先走る
- 丁寧さにかける
- 直感で解く
- 面倒くさがる
という欠点があります。
算数の計算問題から数問もミスをしていたにも関わらず、息子の話では、
 息子
息子時間が余ったから最後の問題を頑張った!
頑張ったのはいいけど、最初の計算問題でミスしているじゃん(泣)
息子の場合は、手を動かすよりも、頭で考えてポッと答えを出してしまうので、精度が不安定なんです。
一発で答えを出せるくらい正解率がよければいいのですが、これまた焦り具合やちょっとしたことで不安定に。
なので、
 わたし
わたし手を動かして計算過程をちゃんと書いて~!
と6年生の最後まで言い続けていました。
お子さんの答えがあっているかだけでなく、どうやって問題に向き合っているのか、5年生のうちに見てあげるといいと思います。
6年生になってからやり方が通用しなくなってくることもあるので、習慣化は早めの対応をおすすめします。
春:国語の壁と「なんとなく読む」くせ

5年生の春。算数や理科はまずまずでしたが、国語でつまずきました。
と言っても、4年生の時から苦戦していたんですけどね…。
“なんとなく読んで、なんとなく答える”
という感じで、線引きの練習をしていても、いざテストになると問題用紙がきれい!
読書と違って「読解」は難しいですね。
病院では
 医者
医者この子は言わないとわからないタイプ。教えてあげてくださいね
と言われたこともあり、心情理解の弱さも課題でした。
(※のちに、精神年齢が2歳低いと病院で診断されました。)
人の気持ちを理解しにくい、言葉通りに受け取ってしまって裏の気持ちなどが読めない、漢字を書くことが嫌い…
今思えば、発達凸凹の特性が絡んでいる部分が息子にはあったんだなと思います。
今までお会いしたママたちのお話では、国語が得意!という発達凸凹のお子さんが、たくさんいらっしゃいました。強みとなる特性もあります。
私も国語が苦手だったので、一緒に読解のコツを勉強し始めました。
日能研の国語テキストがわかりにくい!おすすめ教材
私は昔、「国語ができるようになるためには、たくさん本を読んで!」と言われましたが、本を読むだけで国語ができるわけではないじゃ~ん!と思っていました。
読書をして楽しむだけでは、テストの点数が上がらないことにやっと気付いたわけです。
しかも、日能研の国語のテキストは解答が説明不足でポイントがわかりにくい!
そこでおすすめなのが、四谷大塚の予習シリーズ。
解説がわかりやすく、日能研より文法問題もたくさんあります。
予習シリーズは、塾生以外でも購入できますので、他教科のテキストもチェックしてみてくださいね。
国語の読解のコツを勉強してみた当時の様子はこちらで書いています。
夏前:学校行事で生活リズムが狂う

6月は学校行事が続き、勉強に使える時間がぐっと減りました。
体力的にも疲れやすい時期で、机に向かっても集中が続かないことが増えました。
応用問題で点を落とすことが多くなり、
 わたし
わたしやっぱりリズムが崩れると勉強に出るなあ…
と実感。
特性のある子どもは、環境の変化に敏感です。
テストの後日受験(振替休日にテスト&3コマの授業)をしましたが、平日の時間もずれこみ、疲れもたまり、良い結果とはなりませんでした。
入試本番は連日の試験、1日に午前と午後で2校の受験など、試験体力が必要になってくるんですよね。
そうなると、少しでも子どもの心のゆとりや、睡眠時間の確保も考えないと…
母はマネージャー業だなと思います。(私は敏腕マネージャーではありませんが…)
秋:子どもからよく出てくる言い訳

秋ごろになると、少しずつテストで気を付けるべきことがわかってきたようです。
実際にテスト本番で
検算をしている?
線引きをしている?
聞かれていることに答えている?
4教科を見ていても、まだ丁寧さに欠けている部分はあります。
自宅で復習をすれば落ち着いてできるのですが、時間制限があって初めての問題に直面すれば状況が変わるのもわかります。
が、、、、問題用紙がきれいすぎる…。
テスト結果だけじゃなくて、お子さんのテストの問題用紙の書き込みも見てみると、課題がみつかるかもしれません。
 息子
息子「本番ではちゃんとやる」
「わかってるよ~」
「今回だけ間違えた」
「次は本気出す」
「書かなくてもわかるって」
↑ これ、塾の先生もよく言っていましたが、特に男の子がする発言だそうです。
結局、わかっていない、認めない、やろうとしないところが”ありがち”だと言っていました。
語彙力はコツコツ積み上げが必須
大学受験の影響もあるのかもしれませんが、試験問題の文章もながくなっているし、国語の問題文章も長くなっています。
読むスピード、語彙力、理解力、想像力、まとめる力など、年々、難易度がアップしているようですね。
「すこしはにかんでいる」 → 「すこしは」「にかんでいる」と読み、
 息子
息子お母さん、『にかんでいる』ってな~に?
と聞いてくるので、語彙力も…。
そこで、初心に戻って語彙力アップをゆるく再開。
ガツガツ問題集ではなく、隙間時間に少しずつ語を増やすやり方にしました。
※ この本は息子も気に入っていましたが、今でも人気があるようですね。
テストの復習ノート(妹のとき)
息子のときは親子でいっぱいいっぱいで、復習ノートまで手が回りませんでした。
しかし、2歳下の妹のときは、兄での経験を活かし、歴史と理科でまとめノートを作成。
テストで出てきた内容をまとめノートに書き込みして蓄積させていったんです。
- 似た問題が繰り返し出る
- 問題のコピーを貼る(実験問題など)
- 位置で思い出せる
- イラスト追加で印象UP
など、本人に合っていたようで効果が出ていました。
我が家では手が回りませんでしたが、算数のテスト復習ノートを作成して、オリジナル苦手分野の問題集として何度も復習をしているおうちもあると聞きました。
ただ、ノートづくりは皆さんにおすすめできるものではありません。
お子さんによっても違いますし、結局は親がサポートしなきゃ進まないし、時間もかかるし…
ノートを作らなくても、テストの復習だけはやっておくことをおすすめします。
テストから課題を見つける発達凸凹5年生
① テストに向けての生活リズム
やる気がある日もあれば、ない日もありますよね。
親としても単元ごとに塾の宿題もあるし、学校行事もあるし、焦るし…。
全部完璧にやろうとすると疲れてしまうので、ある程度削って取捨選択することも1つだと思います。
② テストの時間配分対策
テストの時間配分では、見直しのルールを決める、わからない問題は飛ばすなど、対策をお子さんと一緒に考えていく時期です。
算数は「最後の5分で計算を確認」
国語は「文法問題から解く」
こんなふうに解く順番や、見直しの型を作っておくと、安心してテストに向かえます。
③ 結果より“工夫したこと”を褒める
点数だけに注目せず、「計算式をちゃんと書いたね」「見直しできたね」など、その日できたことを伝えると、子どもが前向きになりやすいようにもっていくことで、自信につながります。
つい、「約束したのにやっていない」「何度も言ったのにできていない」と言いがちですが、マイナスポイントは子どもの状態を見て言った方がよいかなと思います。
我が家の経験では、息子がイライラしていたり、気持ちが乗っていないときに言っても「うるさいな~」となりがち。
調子が良い時に、さらっと気を付けたほしいことを言うと素直に受け入れていました。(ネチネチ言わないことがポイント!)
④子どもの苦手ポイントを見つける
ケアレスミスが多いのであれば、字が汚いからなのか、余白の使い方が苦手なのか、ひっ算がずれているのか、問題文を理解できていないのか…
お子さんがどうやって問題に取り組んでいるのかを確認してみてください。
余白の感覚がわからずに、計算をし続けて机に書いてしまう子もいると塾の先生が言っていました。
そんなことわかるだろうと思わず、ちょっとお子さんの問題用紙の形跡を見てほしいと思います。
まとめ:「育っていること」を見ていきたい

1年を振り返ると、5年生は勉強への向き合い方が大きく変わります。子ども自身も成長する時期です。
が、、、息子のように精神年齢が2歳低い中でも、少しずつですが中学受験の生活を通して取り組み方を考え、成長したなと思います。
発達凸凹のある子どもにとって、中学受験は“努力の練習”の時間。
5年生はまだ伸びていく途中。完璧じゃなくて大丈夫です。
焦らずできたことをひとつずつ積み重ねていけば、6年生につながる力を育てると感じました。
6年生で塾を休会することになるけれど…
ちょっと先の話になりますが、息子は6年生の春に、塾を3か月間、休会することになります。
でも、5年生の時の積み重ねがあったからこそ、その後にも復活することができました。
学習内容は5年生がベースとなるので、息切れしない程度に、テストを活用して進んでいってほしいと思います。
国語対策をもっと知りたい方へ
▼国語の苦手対策をもっと読みたい方はコチラ